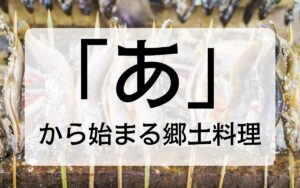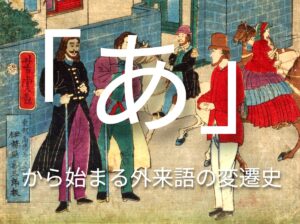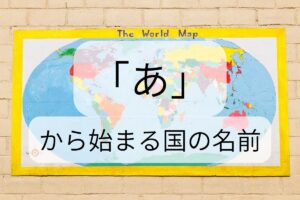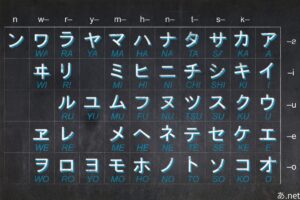茶室に入ると、時間が止まる。
いや、止まるのではない。別の流れ方をする。外の世界とは違う、もっとゆっくりとした、でも確かな時間。
私が茶道を始めたのは、三年前のことだ。
きっかけは単純だった。会社の先輩に誘われて、体験教室に行った。それだけ。
でも、その一服が、私の人生を変えた。
師匠は六十を過ぎた女性だった。背筋がぴんと伸びていて、所作のすべてが美しい。無駄な動きが一つもない。
「お茶を点てます」
そう言って、師匠は茶碗に抹茶を入れた。柄杓で湯を注ぐ。茶筅で点てる。
シャカシャカという音が、静かな茶室に響く。
できあがったお茶を、私の前に置いた。
「どうぞ」
茶碗を手に取る。重い。でも、手に馴染む重さ。
二度回して、正面を避ける。それが作法だと教わった。
口をつける。
苦い。でも、その後に甘みが来る。複雑な味だ。
「どうですか」
「美味しいです」
「そうですか」
師匠は微笑んだ。
「では、次はあなたが点ててみましょう」
私は戸惑った。まだ何も習っていない。
「大丈夫。見たままにやればいいんです」
言われた通りにやってみる。
茶碗に抹茶を入れる。どれくらいの量だろう。適当に、二杓ほど。
柄杓で湯を汲む。重い。こぼれそうになる。
慎重に茶碗に注ぐ。
茶筅を持つ。どう動かせばいいのか。
見よう見まねで、シャカシャカと動かす。
でも、泡立たない。ただ、お湯と抹茶が混ざるだけ。
「もっと速く、でも力を入れすぎずに」
師匠の声に従って、動かし方を変える。
少しずつ、泡が立ってきた。
「そう、それでいいです」
できた。見た目は師匠のとは全然違うけれど、一応お茶の形にはなった。
「飲んでみてください」
自分で点てたお茶を飲む。
味は、さっきと同じはずなのに、違う。
自分で作ったからだろうか。なんだか、愛着がわく。
「どうですか」
「不思議です。こんなに難しいのに、こんなに楽しい」
「茶道は、一生かけて学ぶものです。でも、楽しむのは今日からできます」
それから、私は週に一度、師匠の茶室に通うようになった。
最初は所作を覚えるので精一杯だった。
襖の開け方、座り方、お辞儀の角度、茶碗の持ち方、茶筅の動かし方。
すべてに決まりがある。なぜこうするのか、最初は分からなかった。
でも、続けているうちに、その理由が見えてくる。
この所作は、相手への敬意を表すため。この角度は、美しく見えるため。この動きは、無駄を省くため。
すべてに意味があった。
一年が過ぎた頃、師匠が言った。
「そろそろ、亭主をやってみましょう」
亭主とは、お茶を点てる側のこと。今までは客として学んでいたが、今度は主人として客をもてなす。
緊張した。
茶室を整える。掛け軸を選ぶ。花を生ける。茶碗を選ぶ。
すべてが、客への心遣いだ。
その日の客は、師匠一人だった。
でも、だからこそ緊張する。師匠の目は厳しい。
茶室に入る。師匠が座っている。
挨拶をする。炉に炭をつぐ。釜に水を足す。
一つ一つの動作を、丁寧に。
茶碗を温める。茶を入れる。湯を注ぐ。
茶筅を動かす。
手が震える。茶筅が茶碗に当たる音が、大きすぎる気がする。
でも、止まらずに続ける。
泡が立つ。細かい泡。今までで一番うまく点てられた気がする。
師匠の前に、茶碗を置く。
「どうぞ」
師匠は茶碗を手に取った。二度回す。口をつける。
一口、二口、三口。
飲み終えて、茶碗を見つめる。
長い沈黙。
「良いお茶でした」
その一言が、嬉しかった。
「でも」
師匠は続けた。
「あなたは、まだ頭で点てています」
「頭で、ですか」
「所作を思い出しながら、次はこうして、その次はこうして、と考えながらやっている。それでは、心が入らない」
その通りだった。
私は失敗しないように、手順を間違えないように、必死に思い出しながらやっていた。
「茶道は禅です。無心になりなさい。考えずに、体に任せる。そうすれば、自然と心が入ります」
無心。
それは、座禅で学ぶことだと思っていた。でも、茶道も同じなのか。
「次は、何も考えずにやってみましょう」
師匠はそう言って、客の位置に戻った。
もう一度、茶を点てる。
今度は、手順を思い出さない。体が覚えている動きに任せる。
茶碗を手に取る。軽い。いや、重さを感じない。
茶を入れる。自然な量。
湯を注ぐ。流れるように。
茶筅を動かす。リズムがある。音楽のように。
ああ。
これか。
体が、勝手に動いている。私が点てているのではない。茶が、点てられている。
主語が消える。
私も、茶も、動作も、すべてが一つになる。
泡が立つ。美しい泡。
師匠に出す。
師匠は飲んだ。
「今のです」
そう言って、微笑んだ。
「今のお茶には、心がありました。あなたの心が、茶碗の中にある」
涙が出そうになった。
こんなに嬉しいことがあるだろうか。
二年目の冬、大きな茶会があった。
師匠の知人たちが集まる、正式な茶会。私も亭主の一人として参加することになった。
当日、朝から準備をした。
茶室を掃除する。床の間を整える。道具を並べる。
客が来る。十人ほど。
皆、茶道の経験が長い人たちだ。私のような初心者が点てるお茶を、どう思うだろう。
不安だった。
でも、師匠の言葉を思い出す。
「考えるな。ただ、点てなさい」
一人目の客に、お茶を出す。
二人目、三人目。
だんだんと、リズムができてくる。
緊張が消える。いや、緊張はあるけれど、それを超えた何かがある。
一人一人の顔を見る。この人は、今日どんな気持ちで来たのだろう。
この人のために、最高の一椀を。
そう思いながら点てる。
すべての客にお茶を出し終えた。
疲れた。でも、心地よい疲れだ。
茶会が終わり、客が帰った後、師匠が言った。
「素晴らしかったですよ」
「ありがとうございます」
「お茶は、一期一会です。今日のこの茶会は、二度とない。だから、一椀一椀が尊い」
一期一会。
その言葉が、胸に染みた。
師匠との出会いも、一期一会。
今日の客たちとの出会いも、一期一会。
この瞬間も、二度と来ない。
だから、今を大切に生きる。
それが、茶道の教えだった。
三年が経った今、私は師匠から免許を頂いた。
自分で茶室を持つことはできないけれど、どこかで亭主として茶を点てることができる。
でも、免許を取ったからといって、完成したわけではない。
茶道に、終わりはない。
一生かけて、学び続ける。
それが、私の道だ。
今日も、私は茶を点てる。
茶碗を持ち、湯を注ぎ、茶筅を動かす。
その一つ一つの動作に、心を込める。
この一椀が、誰かの人生を変えるかもしれない。
私がそうであったように。
茶室は、今日も静かだ。
でも、その静けさの中に、すべてがある。
過去も、未来も、今も。
すべてが、この一椀の中に。
【執筆後記】『あ』の音と表現について
今回選んだ「ああ」は、タイトルと本文の二箇所に使いました。タイトルは「ああ一期一会」、本文では無心でお茶を点てている最中の「ああ。これか」という気づきの瞬間です。
茶道における「点前」は、極めて様式化された所作の連続です。しかし、その形式を超えたところに、真の茶の心がある。頭で考えて動くのではなく、体が自然に動く。その境地に達した瞬間、主人公は「ああ」と漏らします。
この「ああ」には、長年の疑問が解けた安堵と、新しい世界が開けた驚きが同時に含まれています。言葉で説明されても分からなかったことが、体験を通して一瞬で腑に落ちる。その瞬間を、最も原初的な音で表現しました。
物語には感動という感情を織り込みました。ただし、大げさな感動ではありません。静かな、深い感動です。師匠の一言に涙が出そうになる。その繊細な心の動きこそが、茶道の本質だと思います。
「一期一会」という言葉には、すべての出会いが一度きりであるという無常観と、だからこそ今この瞬間を大切にするという積極性が共存しています。「ああ」という感嘆も同じです。過去への感慨と、未来への決意が、一つの音に凝縮されている。茶道と禅が交わる地点に、この言葉があるのだと思います。