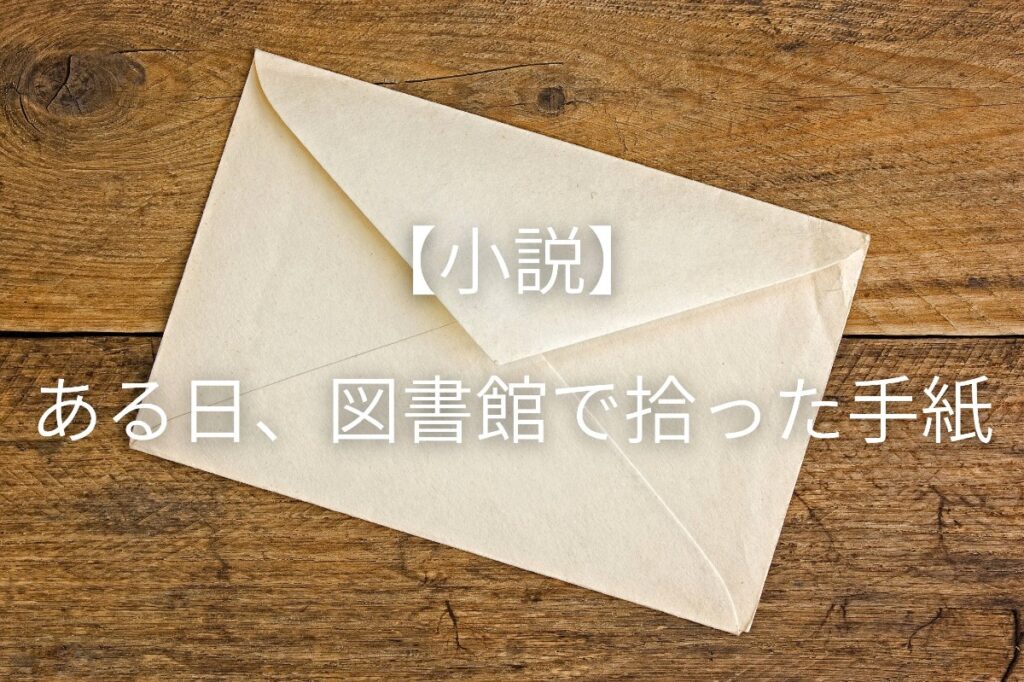
三月の図書館は、いつもより静かだった。卒業シーズンが終わって新学期が始まるまでの、ほんの数日間の空白期間。私は司書のアルバイトとして、返却された本を棚に戻す作業をしていた。
古い文庫本を手に取ったとき、ページの間から一枚の便箋が滑り落ちた。拾い上げると、丁寧な筆記体で書かれた英文が目に飛び込んできた。内容を読み進めるうちに、これが誰かの未送信のラブレターだと気づいた。差出人の名前も、宛先もない。ただ、愛おしさと切なさが行間に滲んでいる文章だけがそこにあった。
手紙を読み終えたとき、私の胸に不思議な感覚が広がった。誰が、どんな思いでこの手紙を書いたのだろう。そして、なぜ送らなかったのだろう。もしかしたら勇気が出なかったのか、それとも想いを伝えるタイミングを逃してしまったのか。
あぁ、と小さく息を吐いた。
私自身にも似たような経験があった。大学二年生の春、同じ授業を取っていた先輩に憧れていた。図書館でよく見かけるその人は、いつも窓際の席で専門書を読んでいた。話しかけたいと思いながらも、結局何も言えないまま、その人は卒業していった。
手紙を本に挟み直そうとして、ふと思い直した。これはもしかしたら、誰かにとって大切な記憶の欠片かもしれない。捨てるわけにはいかない。かといって、落とし物として届けるのも何か違う気がした。
結局、私はその手紙を自分の手帳に挟んで持ち帰ることにした。家に帰ってから改めて読み返すと、書き手の温度が伝わってくるようだった。言葉にできない想いを必死に言葉にしようとした痕跡が、インクの濃淡に残っている。
夜、ベッドに横になりながら考えた。もし私があのとき勇気を出していたら、今は違う日々を過ごしていただろうか。でも、伝えられなかった想いにも意味があるのかもしれない。それは心の中で静かに熟成されて、いつか別の形で現れるものなのかもしれない。
翌朝、図書館に出勤すると、カウンターに一人の男性が立っていた。三十代半ばくらいだろうか。「あの、昨日この本を返却したんですが、中に大切な手紙を挟んだままだったかもしれなくて」と、少し焦った様子で尋ねてきた。
私は手帳から手紙を取り出して、彼に手渡した。彼は安堵の表情を浮かべて何度も礼を言った。そして、少し恥ずかしそうに笑いながら言った。「実は、今日これを本人に渡すつもりなんです。十年越しで」
十年。その言葉の重みに、私の心が震えた。
彼が図書館を出ていく背中を見送りながら、私は窓の外の桜の蕾を見つめた。まだ開花には早いけれど、確実に春は近づいている。伝えられなかった想いも、いつか花開く時が来るのかもしれない。そう思うと、胸の奥がじんわりと温かくなった。
あの先輩に会えることはもうないだろう。でも、あの日々があったからこそ、今の私がある。憧れという感情は、人を前に進ませる力にもなるのだと、ようやく理解できた気がした。
【執筆後記】『あ』の音と表現について
今回の小説で使用した「あぁ」という感嘆表現は、主人公が手紙を読み終え、深い思索に沈む瞬間に配置しました。この「あぁ」は、単なる溜息ではなく、他者の未完の恋に触れた瞬間、自分自身の過去の想いが呼び覚まされる、内省的な転換点を示す音として機能しています。
言語学的に見ると、「あ」という母音は日本語の五十音の起点であり、最も自然に発せられる開放的な音です。「あぁ」と伸ばすことで、感情の深さと持続性を表現できます。この作品では、憧憬という感情を扱いましたが、「あぁ」という音には、到達できない対象への想いと、それを受け入れる諦念が同居しています。
「あ」の音が持つ始まりの象徴性。物語の中で主人公は、過去の恋を思い出しながらも、それを新しい自己理解の契機へと転換させていきます。「あぁ」という一音が、過去を振り返る音であると同時に、新しい認識へと踏み出す最初の音でもあるという二重性が、この小説のテーマと響き合っています。
また、「あ」で始まる「ある日」という冒頭表現も、物語の始まりを告げる言葉として機能しており、偶然性と必然性の両面を含んでいます。日常の中の小さな発見から人生の真理へと至る過程を、「あ」という音が象徴的に支えているのです。




