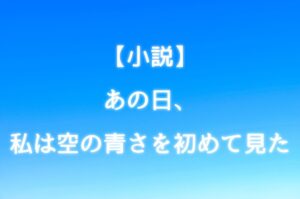私がこの奇妙な体験を記録しておこうと思ったのは、あれから三日が経った今でも、あの感覚が消えないからだ。
事の始まりは、先月末に引っ越した古いアパートの一室だった。家賃が驚くほど安く、駅からも近い。不動産屋の担当者は少し言いよどんだが、前の住人が夜逃げしたというだけで、特に問題はないと言った。
部屋は六畳一間。南向きの窓からは隣のビルの壁しか見えないが、私には十分だった。ただ一つ、妙なものがあった。クローゼットの奥に、大きな姿見が据え付けられていたのだ。
鏡は縦長で、木製の重厚な枠に囲まれている。表面には細かい傷が無数についていて、古いものだとわかった。取り外そうとしたが、壁に固定されていて動かせない。仕方なく、そのままにしておいた。
最初の異変に気づいたのは、引っ越して一週間後の夜だった。
ふと目が覚めると、部屋の中に誰かがいる気配がした。時計を見ると午前二時過ぎ。耳を澄ますと、微かに何かが動く音がする。クローゼットの方からだった。
心臓が早鐘を打った。泥棒だろうか。いや、この狭い部屋に侵入者が隠れられる場所などない。それでも音は確かに聞こえる。
私は勇気を振り絞って、クローゼットの扉を開けた。
そこには誰もいなかった。ただ、姿見が静かに立っているだけ。鏡に映った自分の顔を見て、私は安堵のため息をついた。気のせいだったのだろう。
しかし、鏡から目を離そうとした瞬間、異様なことに気がついた。
鏡の中の私が、わずかに笑っていたのだ。
いや、笑っているというより、口元が不自然に歪んでいた。私は笑ってなどいない。むしろ緊張で顔がこわばっている。なのに鏡の中の私は、まるで何かを知っているかのような表情を浮かべていた。
慌てて鏡から離れ、扉を閉めた。その夜、私は一睡もできなかった。
翌日、理性が戻ってきた。疲れていたのだ。引っ越しの疲労と、新しい環境への不安が、幻覚を見させたに違いない。そう自分に言い聞かせた。
だが、その夜もまた、同じことが起きた。
午前二時、目が覚める。クローゼットから微かな音。扉を開けると、鏡の中の私がまたあの表情をしている。しかも今度は、鏡の中の私の背後に、誰かの影が見えた気がした。
あ? と声が漏れた。振り返っても、当然誰もいない。もう一度鏡を見ると、影は消えていた。
私は鏡に向かって話しかけてみた。
「誰だ。何が目的だ」
鏡の中の私は、ゆっくりと首を傾げた。私は首を傾げていないのに。
恐怖が全身を駆け巡った。これは幻覚ではない。何かが、確実にそこにいる。
次の日、私は図書館で調べ物をした。鏡にまつわる怪異、心霊現象、精神疾患。あらゆる可能性を探った。そして、一つの仮説に辿り着いた。
鏡は、もう一つの世界への窓なのではないか。
私たちが見ている鏡像は、単なる光の反射ではなく、並行世界に存在する自分自身なのかもしれない。そして、何らかの理由で、その境界が薄くなっている。
馬鹿げた考えだと思った。しかし、他に説明がつかなかった。
その夜、私は実験をすることにした。午前二時まで起きていて、鏡の前に座る。そして、じっと観察する。
時間が来た。クローゼットの扉を開け、鏡の前に正座した。
最初は何も起きなかった。鏡は普通に私の姿を映している。五分、十分、十五分。変化はない。
諦めかけたとき、鏡の表面がわずかに揺らいだ。
水面のように、鏡がゆっくりと波打つ。そして、鏡の中から手が伸びてきた。
私の手だった。いや、私とそっくりな誰かの手。その手は空中で止まり、まるで招いているかのように動いた。
私は理解した。あちら側の私が、こちらに来ようとしている。そして同時に、こちら側の私を、あちらに引き込もうとしている。
鏡に触れてはいけない。そう直感した。
私は後ずさりし、クローゼットの扉を閉めた。鍵をかけ、その上から重い本棚を押し当てた。
それから三日間、私はクローゼットを開けていない。夜になっても、もう音は聞こえなくなった。代わりに、自分の中に妙な空虚感が広がっている。
まるで、何か大切なものを失ったような感覚。いや、もしかしたら本当に失ったのかもしれない。あの鏡の向こうにいた私は、もう一人の自分だったのだから。
明日、引っ越しの手続きをするつもりだ。この部屋にはもう、いられない。
でも時々考える。もし私があのとき、鏡に手を伸ばしていたら、どうなっていただろうか。向こう側の世界は、こちら側とどう違うのだろうか。
そして何より気になるのは、私がこちら側に留まっているという確信が、もう持てないことだ。
【執筆後記】『あ』の音と表現について
今回使用した「あ?」という感嘆詞は、語り手が鏡の中に異様なものを認識した瞬間の、理解を超えた困惑を表現するために選びました。疑問符を伴うこの「あ」は、単なる驚きではなく、認識が追いつかない事態への戸惑いを含んでいます。
小説では日常と非日常の境界が曖昧になる瞬間が多く描かれます。その転換点で発せられる言葉は、論理的な思考が停止する瞬間を示すものでなければなりません。「あ?」という短い音は、まさにその機能を果たしていると考えます。
「あ」という母音は、最も原始的な発声です。赤ん坊が最初に発する音であり、言語以前の反応です。恐怖や驚愕といった強い感情に直面したとき、人は複雑な言葉を紡ぐ前に、この単純な音を発します。それは理性のフィルターを通過する前の、生の反応なのです。
この物語では、鏡という日常的な物品が、突如として不気味なものへと変貌します。その瞬間に「あ?」という言葉を配置することで、読者にも同じ認識の混乱を共有してもらえればと思いました。疑問符が付くことで、語り手自身も自分の感覚を疑っている様子が伝わるのではないでしょうか。