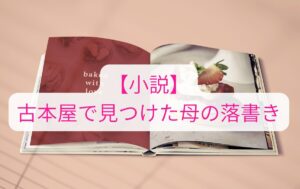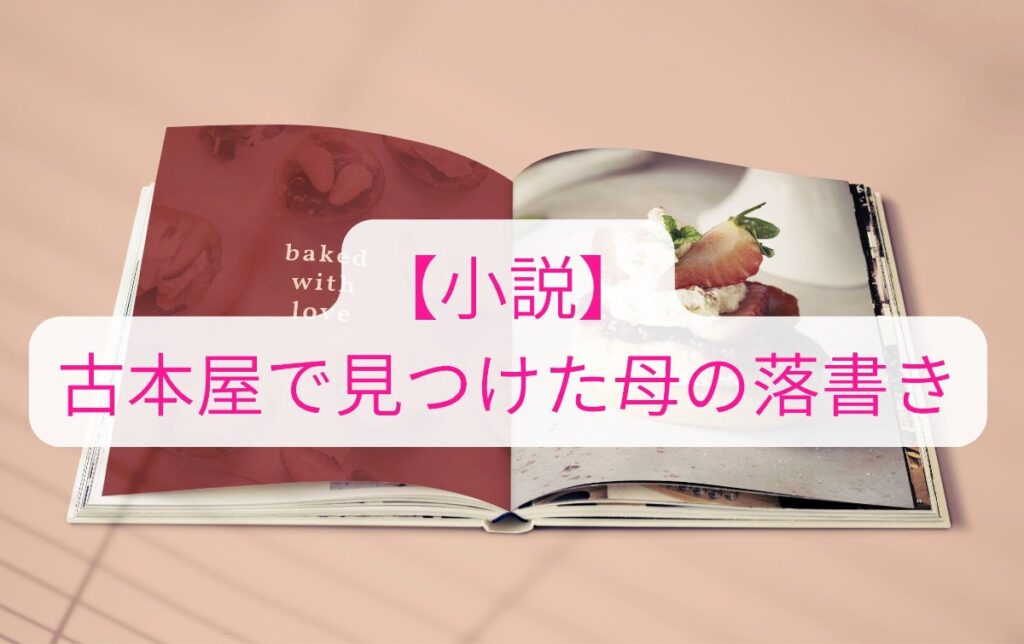
商店街の奥にある古本屋は、いつ行っても薄暗くて静かだ。店主のおじいさんは本を読むことに夢中で、客が来てもあまり顔を上げない。私はそんな雰囲気が好きで、月に一度は必ず立ち寄る。
今日は昭和の料理本を探していた。最近、母が作っていた料理を再現したくなったのだ。母は五年前に他界した。料理上手だった母の味を思い出そうとしても、記憶はぼんやりとしている。レシピを残してくれていたらよかったのに、と何度も思った。
本棚の奥から一冊の料理本を引き抜いた。昭和四十年代に出版された、黄ばんだページの家庭料理集。パラパラとめくっていると、ページの余白に鉛筆で書かれた文字が目に入った。
「砂糖は大さじ2ではなく1.5で」
その字を見た瞬間、心臓が跳ねた。母の字だ。間違いない。あの丸みを帯びた、少し右上がりの筆跡。震える手でページをめくると、他にもいくつか書き込みがあった。
「醤油は最後に入れると香りが立つ」「じゃがいもは小さめに切る」
母の声が聞こえてくるようだった。この本は母が若い頃に使っていたものに違いない。結婚前か、結婚してすぐの頃だろうか。まだ私が生まれる前の、母の姿が浮かんでくる。
レジに持っていくと、店主のおじいさんが値札を確認した。三百円。私は千円札を出しながら聞いた。「この本、どこから仕入れたか覚えていますか」
おじいさんは首を傾げた。「さあ、もう何年も前だからねえ。遺品整理で引き取ったものかもしれないし、誰かが持ち込んだのかもしれない」
母が手放したはずはない。きっと、実家を処分したときに誰かが古本屋に出してしまったのだろう。私が知らないうちに。
家に帰って、本を開いた。母の書き込みがあるページには付箋を貼っていった。肉じゃが、筑前煮、かぼちゃの煮物。どれも母がよく作っていた料理だ。
週末、母のレシピ通りに肉じゃがを作ってみることにした。じゃがいもを小さめに切り、砂糖は大さじ1.5、醤油は最後に。手順を忠実に再現していくと、不思議なことに母と一緒に台所に立っているような気持ちになった。
煮込んでいる間、私はリビングのソファに座って、改めて料理本を読み返した。母の書き込みは全部で十二箇所あった。どれも実用的なメモで、母の几帳面な性格が表れている。
そのとき、ふと気づいた。巻末のページに、料理とは関係のない文字が書かれていた。
「幸せになりたい」
あ。
声にならない声が喉から漏れた。その短い一文が、若き日の母の心の叫びのように感じられた。母にもこんな時期があったのだ。未来が見えなくて、ただ漠然と幸せを求めていた時期が。
私は母のことを、いつも完璧な母親としてしか見ていなかった。料理も家事も完璧で、いつも笑顔で、何でもできる人。でも、母だって若い頃は迷いながら生きていたのだ。幸せを探しながら、少しずつ自分の人生を築いていったのだ。
台所から甘い香りが漂ってきた。火を止めて、蓋を開ける。湯気の向こうに、母の笑顔が見えた気がした。
肉じゃがを口に運ぶ。味は、記憶の中の母の味とほとんど同じだった。完璧に同じではないけれど、これでいいのだと思った。母も最初からうまく作れたわけではなかったはずだ。試行錯誤を重ねて、あの味にたどり着いたのだ。
翌日、私は料理本を本棚に大切にしまった。そして、新しいノートを買ってきた。自分なりのレシピ帳を作ろうと思ったのだ。母がそうしたように、私も自分の言葉で料理を記録していこう。
ノートの最初のページに、母の肉じゃがのレシピを書いた。材料、手順、火加減。そして最後に一行付け加えた。
「母の味を受け継ぐ、私の幸せ」
窓の外では、春の日差しが優しく降り注いでいた。母の書き込みがなければ、私はこの幸せに気づけなかったかもしれない。古本屋で偶然見つけた一冊の本が、母と私をつないでくれた。
今、私は母が探していた幸せが何だったのか、少しわかる気がする。それは誰かに料理を作り、その人が美味しいと笑ってくれること。日常の中にある、小さくて確かな喜び。母はそれを見つけて、私に伝えてくれたのだ。
料理本の表紙を撫でながら、私は静かに微笑んだ。ありがとう、お母さん。そう心の中で呟いた。
【執筆後記】『あ』の音と表現について
この小説で使用した「あ」という感嘆は、主人公が母の「幸せになりたい」という書き込みを発見した瞬間に配置しました。ここでの「あ」は、驚きと発見、そして深い感動が同時に押し寄せる複雑な感情を一音で表現しています。言語学的に見ると、「あ」という最も短い母音は、言葉にならない感情が溢れ出る瞬間を捉えるのに最適です。長い感嘆(「あぁ」など)ではなく、一文字の「あ」を選んだのは、衝撃の瞬間性と、その後に続く沈黙の重みを表現するためです。
主人公は亡き母の書き込みを通じて、母の人間らしさと、自分に残してくれたものの価値に気づいていきます。「あ」という音は、その気づきの瞬間を鮮明に刻印する役割を果たしています。
「あ」という音が持つ開示性。主人公は母の本当の姿、完璧ではなく迷いを持った一人の人間としての母を発見します。その瞬間、「あ」という声とともに、主人公の心の扉が開かれます。母音「あ」は口を大きく開けて発音するため、文字通り心を開く動作と連動しているのです。
また、物語全体が「ある日の発見」から始まり、「ありがとう」という感謝で終わる構成になっています。どちらも「あ」で始まる言葉です。この対称性は意図的なもので、「あ」という音が持つ始まりと受容の両義性を象徴しています。偶然の出会いから感謝の気持ちへと至る心の旅路を、「あ」という一つの音が貫いているのです。