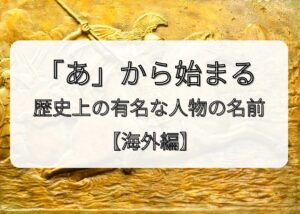今日、図書館で辞書を眺めていたら、不意に気づいた。私の名前である「あ」という一文字が、この国の言葉の最初に位置しているということに。
五十音の筆頭。アルファベットでいえばAだ。始まりの音。開口一番の響き。人間が最初に発する声に最も近い音韻。そう考えると、私という存在は偶然ではなく、何か必然的な配置によってこの世に送り込まれた気さえしてくる。
思えば子どもの頃、自己紹介のたびに笑われた。「名前、あ、だけなの」って。でも母は言っていた。「あなたはすべての始まりなのよ」と。当時は意味が分からなかった。ただの変わった名前としか思えなかった。
けれど今は違う。三十歳を過ぎて、ようやく理解し始めている。
あぁ、そうか。私は言葉を発する前の、その一瞬手前に存在しているのかもしれない。誰かが何かを言おうとして、唇を開く。そのわずかな間に漂う、まだ形にならない想い。それが「あ」という音になる。驚き、発見、感嘆、疑問、すべての感情が言語化される直前に通過する、透明な門のような存在。
今朝、駅のホームで見知らぬ老人が転びそうになった。私は咄嗟に手を伸ばした。老人は私の顔を見て、何か言おうとして口を開けた。でも言葉は出てこなかった。ただ「あ…」という音だけが、空気を震わせた。
その瞬間、私は理解した。感謝も、驚きも、恥ずかしさも、安堵も、すべてが混ざり合った複雑な感情が、まだ言葉という形を得る前の段階で、「あ」という音に凝縮されていた。それは完璧だった。どんな「ありがとう」よりも、どんな「すみません」よりも、その「あ…」は真実だった。
帰宅して鏡を見た。私という人間は、他人にとって常に「あ」の瞬間を運んでくる存在なのかもしれない。名刺を渡すと、相手は必ず戸惑う。説明を求められる。そのとき相手の口から漏れるのは「あ、そうなんですか」という言葉だ。
私は誰かの人生において、小さな気づきの入口になる。会話の始点になる。疑問符になる。驚嘆符になる。そして何より、言葉にならない感情が、初めて外へ出ようとするときの産声になる。
夕暮れ、部屋の窓から街を眺めた。無数の人々が歩いている。それぞれが複雑な感情を抱えて、言葉を探しながら生きている。でも、その誰もが一日に何度も「あ」という音を発しているはずだ。気づいたとき、驚いたとき、理解したとき、失敗したとき。
私たちは皆、始まりの音を共有している。どんなに複雑な思想も、壮大な物語も、深遠な哲学も、最初はこの「あ」という、たった一音から始まっている。母が言っていた意味が、今ならわかる。
私は言葉の門番なのだ。感情と言語の境界に立ち、すべての想いが形になる直前の、あの純粋な瞬間を守っている。それが私の名前に込められた、静かな使命なのかもしれない。
明日も私は「あ」として生きる。誰かの驚きになり、誰かの気づきになり、誰かの言葉の始まりになる。それは決して大きな存在ではないけれど、なくてはならない存在だ。すべての対話は、すべての物語は、この一音から始まるのだから。
【執筆後記】『あ』の音と表現について
今回の小説では「あぁ」という長音を含む感嘆を選びました。この選択は、主人公が自己の存在意義に気づく瞬間を表現するために意図的なものです。「あ」という単音が持つ瞬発的な驚きに対し、「あぁ」は理解へと至る過程の時間的な流れを含んでいます。音韻学的に見れば、母音の延長は感情の深化を示します。
この物語で描いた感情は、言葉にならない何かが言語化される直前の状態です。それは名づけえぬ感覚であり、まさに「あ」という音素が担う役割そのものでした。人間の発話において最も制約の少ない開口母音である「あ」は、喉を最も自然に開いた状態で発せられます。これは赤ん坊が最初に発する音でもあり、人類普遍の始原的な声です。
哲学者ハイデガーは「言語は存在の家」と言いましたが、私はその家の入口に「あ」という音が立っていると考えています。すべての思考、すべての感情は、この透明な門を通過して初めて他者と共有可能になる。主人公の名前を「あ」としたのは、その境界性を人格化したかったからです。私たちは日々、無数の「あ」の瞬間を生きています。その一つ一つに、言語化以前の純粋な真実が宿っているのです。